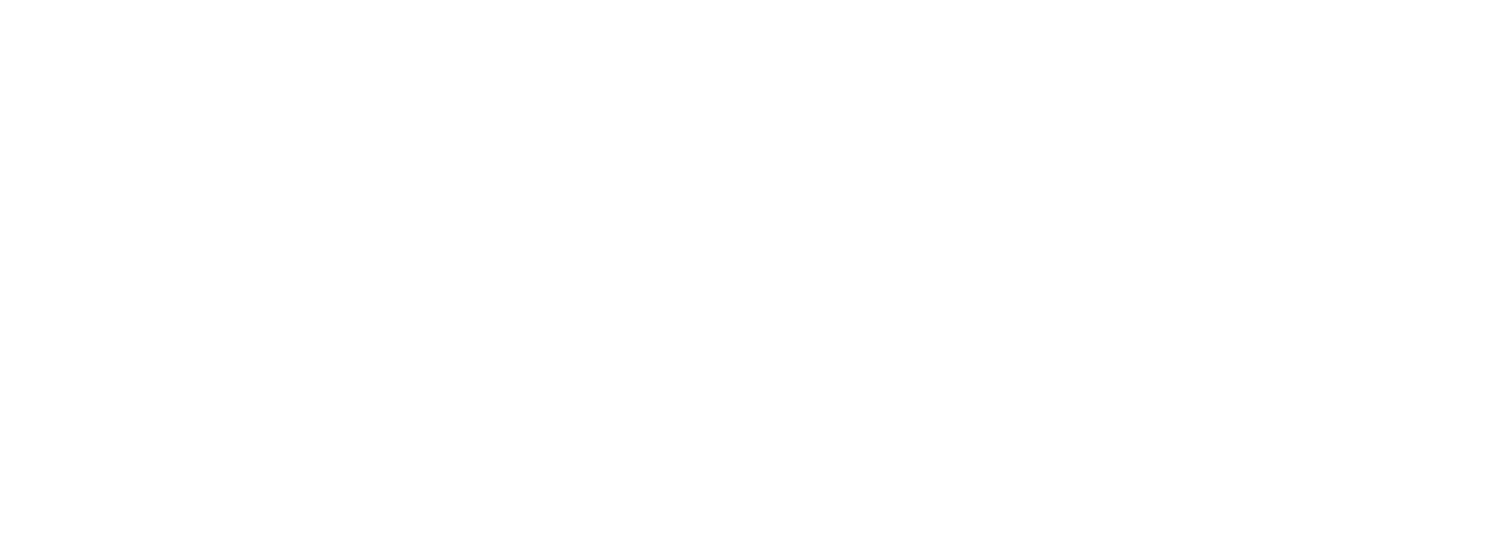


鈴木 謙介
関西学院大学准教授。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター客員研究員。
1976年福岡県生まれ。専攻は理論社会学。2002年の『暴走するインターネット』以来、ネット、ケータイなど、情報化社会の最新の事例研究と、政治哲学を中心とした理論的研究を架橋させながら、独自の社会理論を展開している。
視覚や聴覚からではなく、言語化できない体感的な刺激で呼び起こされる、自分の中に刻まれたエピソード、考える前にわき上がってくる感覚。「体が覚えている」とでも言うべきオーセンティシティ(本物性)について、鈴木謙介さんに寄稿していただきました。
記憶を呼び覚ます感覚刺激は変化する
日常生活において私たちはよく「体が覚えている」という経験をする。真夜中、家族を起こさないようにと電気をつけずに自宅の中を歩いていても、階段を上り下りしたりドアを開けられたりするといったことだ。こうしたことが可能なのは、歩き慣れた家の構造についての情報が手続き記憶として脳内に蓄積されているからだと考えられる。このような事例は、自分の行動が意識される前に実行されるからこそ「体が覚えている」としか言いようのない感覚を伴う。しかし、誰かとどこかに行った、自分が何かをして考えたといったエピソード的な記憶についても「体が覚えている」とでも言うべき現象が見られるのではないだろうか。それは例えば、元恋人と旅行に行った際に買ったキーホルダーを見つけたときや、思春期に流行していたポップミュージックが耳に入ってきたときに、懐かしい感情を掻き立てられるといったことだ。そこでは意図的に思い出そうとしたわけではないのだが、視覚や聴覚を刺激されることで、体で覚えていた記憶が呼び覚まされるわけだ。
ここで私がこうしたありきたりの例を挙げた理由は、エピソード的な記憶を引き出す刺激が、視覚や聴覚に偏りがちであることに注意を促したかったからだ。目や耳といった器官に神経細胞が集中していることや、人類が発達した知能で得た知識を他の個体に引き継ぐために発明した「言語」などのメディアが視覚・聴覚的な刺激を伴うものであったことから、集合的な「記憶」はこれまで、見る・聞くといったことで伝播される傾向にあった。
そのように考えれば、たとえば現代社会において「広告」というメディア、つまり商品に関する情報伝達手段が視覚的・聴覚的な刺激に偏っていることにも納得がいく。企業名や商品名を連呼する古典的なものから、印象的なCMソングなどのサウンドアイデンティティの制作、お茶の間に対する見慣れたタレントの起用、インパクトのあるコピーライティング……これらはすべて、視覚と聴覚で歴史を形成してきた私たち人類の取りうる行動の延長にある。
しかし、そうした「視聴覚優位」の記憶というものは、いわば近代的な機制だとも言える。伝統社会に目を向ければ、たとえば通過儀礼などの宗教的儀式において重要なのはむしろ、特殊なお香の匂いであり、儀礼でのみ口にされる酒の味であり、「熱い」とか「痛い」といった身体的な苦痛であった。これらは、言語と関連の深い視聴覚情報ほど明確に言語化しにくいが、それだけに「体が覚えている」という感覚を、強く刺激するものだと考えられる。
言語化しやすい視聴覚情報と、言語化しにくいその他の感覚刺激。どちらがいいかという判断は下せないが、近年のテクノロジーは、確実に後者の刺激を活用する方向に進化しつつある。スマホの登場によって情報は触覚的なものになり、イベントなどでも、キャラクターと触れ合う、ご当地の食を味わうといった「体感的」なものが次々登場し、参加者を集めるようになっている(図)。
このような「体感」がもたらすものは何か。ひと言で表すならそれは「体感的オーセンティシティ」だ。オーセンティシティとは、ある物事を「本物」と感じられることを指す。ずっとテレビや雑誌で見ていたアーティストのライブに行き、彼が歌い出した瞬間に感じる「本物だ!」という認識のことだ。こうした認識が視聴覚に限定されない「体感」と結び付くとき、私たちはそこに、言語化されないオーセンティシティを感じるのである。
そしてその体感的オーセンティシティは、イベントなどのリアルな会場から、情報を手で触れて動かすことが当たり前になりつつあるスマホの小さな画面に至るまで、私たちのオーセンティックな感覚を揺さぶり始めている。それは結果的に「オーセンティックなもの」に関する私たちの記憶すらも書き換え、オーセンティシティを感じるそのあり方にすら変化を及ぼすのかもしれない。