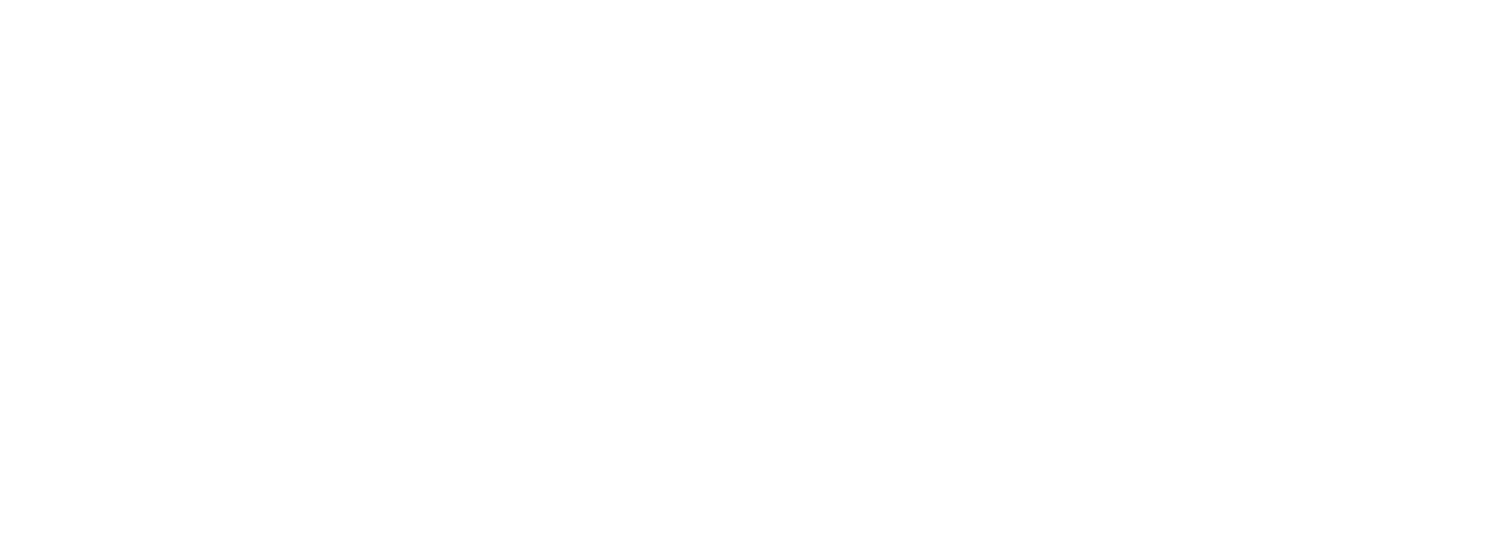

ダンサーが持つ身体表現の技、それを生み出す感覚とはどういったものなのでしょうか?ドイツ・ベルリンを拠点に、ジャンルや文化を超えた表現を繰り広げる振付家/ダンサー、川口ゆいさんにダンスにおける技や身体感覚について話を伺いました。

川口ゆい
6歳よりダンスを始め、現在ベルリンをベースにダンサー、振付家として活躍。他分野とのコラボレーションにも積極的に取り組み、世界各地の国際フェスティバルで、公演やワークショップを行う。
バレエの技に魅了されダンスの世界に進む
—ダンスを始めたきっかけはなんですか?
川口:5歳のときに森下洋子さんが出演する「ジゼル」を見て、森下さんのようになりたくてクラシックバレエを始めました。森下さんの動きには、遠くから見ていた小さな私にも、なぜか伝わるものがあったのです。その後、中学でダンス部に入り、マイケル・ジャクソンやマドンナのストレートで現実にマッチした音楽やダンスに熱中しました。高校卒業後は、ミュージカルで知られる音楽座に入り、舞台に関するさまざまなことを学びました。そこでは、ゲストで来ていたH・アール・カオスの白河直子さんのダンスに衝撃を受けてディープなダンス表現にも興味を持つようになりました。音楽座の解散後は、大島早紀子さん(H・アール・カオス)や山崎広太さんといった振付家の方々と仕事をするようになりました。—本格的にダンスに専念するようになったわけですね。
川口:そうです。山崎さんはもともと舞踏の方で、ワークショップにも参加しました。それがすごく刺激的で面白かった! 形ではなく言葉、特にアブストラクトな比喩で体の動きを誘導するんです。例えば足を一歩動かすにしても、「その1歩で1000年進む」とイメージしてみるんです。すると足の動かし方が違ってきます。自分でも「足が手だと思って立ち上がる」「足が車だと思って歩いてみる」など、頭の中にある体のマッピングをずらして遊んでみたら、思考がすごく開いて、従来の「こう踊るべき」という窮屈さから解放されたと感じました。ベルリンでのカルチャーショックとあえて言語化しないことの意味
—川口さんはベルリンを拠点に活動されてますが、きっかけは何だったのでしょうか?
川口:2001年に公演でベルリンに行ったのですが、公演後に怪我をしてしまい、しばらく現地で療養することになったんです。その滞在で、大きなカルチャーショックを受けました。当時のベルリンには、まだ壁崩壊後に生まれたスクワットや第二次世界大戦時の弾痕が残っており、街自体が未完成という印象でした。いい意味で隙間のある街、やりたいことを試せる街という雰囲気でした。東京はもちろん、ロンドンやニューヨークといったほかの大都市とも違いました。ベルリンでは、ダンスの後に観客からいろいろと聞かれることが多くて、それも新鮮でうれしかったですね。そんなこともあって、あえて質問したくなるような作品を作るようになったかもしれません。—「質問をしたくなる作品」とはどんなものでしょう?
川口:観客に解釈をゆだねる要素がある作品ですね。ダンスには身体言語としての側面があります。例えば、クラシックバレエは西洋的身体言語だし、日本人が手のひらを合わせると祈っているように見えます。それらを多用すると、観客はステレオタイプなイメージをそのまま受け入れてしまう。このことは、さまざまな国で公演をする中で、強く実感しました。現在では、あえてステレオタイプな動きを取り入れたり、逆に排除したり、さまざまなタイプの動きが現れては消えるように振り付けることが多くなりました。もちろん、何かを伝えたいという欲求はあります。理解されたい気持ちと誤解されたくない気持ちのせめぎ合いのような状況になることが、よくありますね。—そのような作品を作るとき、コンセプト自体は言語化してから作るのでしょうか?
川口:具体的なところまでかなり言語化しますが、結論はあえて言語化しないようにしてます。自分の身体が感じていることを大事にして、それを探り続けるという感じです。また、ほかの人とコラボするときは、自分との関係をイメージするのが重要なポイントです。例えば、ピアニストの高瀬アキさんとのデュオを10年ほどやっていますが、アキさんの音の中を旅するというイメージです。ほかの楽器奏者の場合も、音が出ている楽器を見ながら、自分の体の中で反応しているところを探したります。
ピアニストの高瀬アキとのデュオ、「ピアノの中の街」シリーズより。2008年より展開されており、ヨーロッパ各地のフェスティバルにも招聘されている。
触覚とテクノロジーを駆使したステージの試み
—触覚を使った作品も作られていますね。
川口:映像作家の石橋義正さんと共同制作した「Match Atria(マッチャトリア)」ですね。Matchaは抹茶、Atriaは心臓の心房からとっています。元々のインスピレーションは、訪れた客をお茶でもてなすという日本の茶の湯の慣習から来てます。ただしマッチャトリアでは、お茶の代わりに心臓をかたどったオブジェが観客に渡されるんです。そのオブジェはパフォーマンスをするダンサー、つまり私の心臓の鼓動が送り込まれ、リアルタイムに振動するようになってます。
映像作家の石橋義正との共同制作「Match Atria(マッチャトリア)」。3D映像に彩られた空間で、ダンサー川口ゆいのパフォーマンスが繰り広げられる。
—心拍の変化を感じながら観るということですね。
川口:ええ。マッチャトリアはもともとは、自分の心臓を振動として感じる「心臓ピクニック」というワークショップに参画したことがきっかけとなっています。鼓動を手のひらで感じた瞬間、周りを歩いている人にも心臓があるということをリアルに実感したんです。同時に、すごく抽象的なものだった東京の人混みがすごく身体的に感じられるようになった。そういった感覚を観客の皆さんにも体験してほしいという思いがありました。マッチャトリアはある意味、私なりのおもてなしといえる作品です。—現在取り組んでいるテーマを教えてください。
川口:まだ形になっていませんが、クライオニクス(人体冷凍保存)をテーマにした作品を制作したいと考えています。「人間は二度死ぬ。一度目は肉体の死、二度目は忘れられた時」という言葉がありますが、現代では、自分の情報はデジタルデータとしては半永久的に残せるようになってきています。そういった時代に死は何を意味するのか、そんなことも考えています。
「Match Atria(マッチャトリア)」で観客は、ヘッドフォンと3D眼鏡の装着を促され、ダンサーの鼓動が感じられる心臓のオブジェを手渡される。