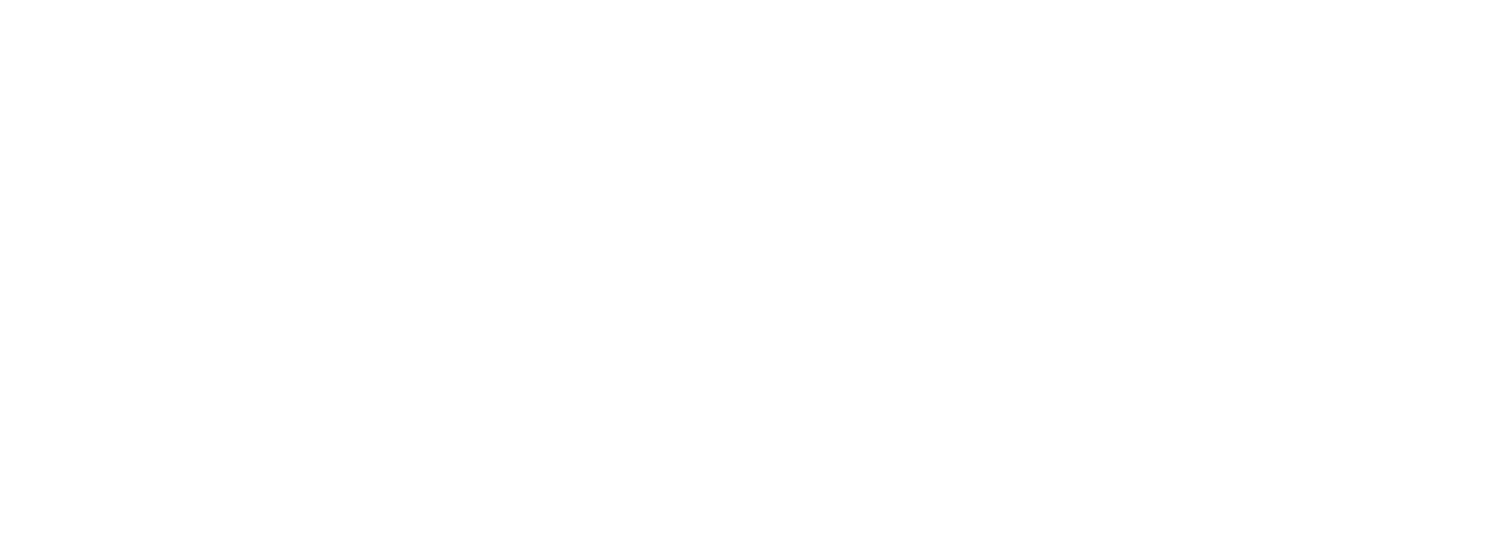

視覚障がい者と晴眼者が一緒に美術作品を観賞し、そこでの対話から作品の新しい見方や意味を発見する「ソーシャル・ビュー」という試みがあります。現在NTTでは、この試みのスポーツ観戦版である「スポーツ・ソーシャル・ビュー」の研究を東京工業大学と進めています。今回はプロジェクトに関わっている3人による鼎談です。
伊藤 亜紗
東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院
環境・社会理工学院准教授 博士(文学)
林 阿希子
NTT サービスエボリューション研究所
2020エポックメイキングプロジェクト 研究主任
渡邊 淳司
NTT コミュニケーション科学基礎研究所
人間情報研究部 主任研究員(特別研究員) 博士(情報理工学)
視覚障がい者とともに盛り上がれるスポーツ観戦方法を探る
林:このプロジェクトはもともと、2020年の東京オリンピックに向けた試みのひとつでした。「多様性」というキーワードのもと、スポーツ観戦に関する障がい者支援に取り組んでいたのです。ただ私自身は、支援というより、違いを楽しむ、違いがあるからこそ価値が生まれる点を意識して進めていました。伊藤:私は以前から障がいに関する研究を行っていたのですが、身体的条件が異なる人との言語によるコミュニケーションに限界を感じていました。特に言語で伝え切れないものが、「お笑い」と「スポーツ観戦」です。両方とも「同期」や「シンクロ」が重要で、みんなでお笑い番組を見ていても、目の見えない人はなぜ笑っているかがわからず、言葉で説明してもタイミングがずれてしまう。スポーツ観戦も同じで、説明を聞いていると乗り遅れてしまいます。また盛り上がりを同期させるには、ピークのタイミングだけを伝達してもダメで、波状に伝えなければならない。「来る! 来る!」というタメのあとに「来たっ!」となって、初めてシンクロできます。それを実現するための手法を開拓したいと、前から考えていました。
渡邊: では、触覚が専門の私の立場から。現在の触覚研究のほとんどは「AからBへ情報(振動)が伝わった」で終わっていますが、私は、「伝わる/伝わらない」を超えて、人と人との間で何かが生まれてくるような共同身体性について研究をしたいと思っていました。加えて、最近のスポーツ伝送は臨場感を伝えようとするものが多いのですが、それが本当にスポーツ観戦という体験のすべてなのかという疑問もあります。むしろ観戦の「場」で起こる何かが重要なのではないかと思うんです。「場」の研究はいろいろありますが、それをスポーツ観戦という文脈でもう一度捉え直したいと考えていました。
ポイントとなるのは「言葉」ではなく「出来事」
林:まず最初に試したのは言語的に状況を説明するというものでした。具体的には、画面に流れる空手の映像を見ながら、視覚障がいの方に内容を説明するというものです。説明するのは合計4人で、2人は空手の未経験者、2人は経験者でした。渡邊:結論からいうと、うまくいきませんでしたね。説明はできていたんですが、やはり言葉だけではわかりにくい。視覚障がい者は置いてけぼりになってしまいました。その後、経験者の私が、空手は呼吸でリズムを作って動くということで、映像の中の選手の呼吸に合わせて机を叩いてみました。そうすると動きのリズムが伝わったんです。そこから、言語ではなく身体的な体験を共有し、リアルタイムにスポーツ観戦をする取り組みが始まりました。
伊藤:ワークショップなどでよく使う「えんたくん」という丸いダンボールのボードがあって、たまたまそれを叩いてみたのが大きな転換点でしたね。「これだ!」と感じました。
林:それから、どのスポーツを観戦するのか、どんな道具を使うのかとか、いろいろと試行錯誤しましたね。卓球がいいのではと思ったのですが、速すぎて無理。飛び込みや体操といった回転するスポーツも難しい。結局、テニス、バドミントン、空手、柔道の4つの競技に行き着きました。
渡邊:テニスの場合は、私と視覚障がい者が向き合って座り、膝の上に円形のボードを渡して叩きながら観戦します。ボードをテニスコートに見立てて、二人がネットの両端に当たる位置に座わるわけです。私はテニスプレーヤーが球を打った位置に当たるボードの場所を手で叩きます。ラリーが続くと、右、左と順に叩くことになりますが、興味深いことに、視覚障がい者も右、左と首を動かして、あたかも球の動きを追っているようになりました。あと、サーブを打つときによくトントンと球を地面にバウンドさせますが、そのリズムも叩いて表現しました。

テニスコートに見立てた円形のダンボールのボードを視覚障がい者と中継者のひざの上に渡して置き、中継者がボールの位置と強さを反映しながらボードを叩く。アウトのときはボードを跳ね上げるなど、アクションも決めておく。視覚障がい者は、ラリーを見る観客のように首を左右に振る動きを見せた。
林:柔道では手ぬぐいを使いました。私と伊藤さんが両端を持ち、視覚障がい者に真ん中を持ってもらいました。そして選手の動きに合わせて2人が手ぬぐいを引っ張り合うんです。引っ張り合うだけじゃなく、フェイントをかけたり重心を崩すような動きも再現したら、そこで試合が行われているようで、視覚障がい者も「実況がなくても楽しめる」と言ってくれました。

中継者二人が手ぬぐいの両端を持ち、視覚障がい者が中央を握る。中継者は、試合中の二人の立場で手ぬぐいを引っ張り合い、上下左右などの動きや強さ、勢いも表現する。試合が決まったときは、勝者が明確にわかるようにした。中継しながらも、そこには別の形の試合が、出来事として生成されている。
伊藤:この体験の要素は2つあって、ひとつは、ラリーのリズムや空手のタメのようなその種目ならではの質感。もうひとつは、ボールの位置や勝ち負けのような実況中継的要素です。質感の上に実況中継を乗せる感じです。今回の種目も、テニスとバトミントンでは、実況中継は近いけれど、テニスボールが跳ねる感じと、バドミントンのシャトルでは質感が違い、空手と柔道は質感は似ているけど、実況中継が違いました。

バドミントンはシャトルが空中を行き交うので、ボードをペンでこすってスイングを表し、シャトルの質感を出すため扇子で耳元に風を起こした。
伝達とは異なる生成的観戦体験とは?
林:実験を振り返ると、視覚障がい者とのスポーツ観戦では、言語的にすべてを伝えようとするのではなく、本質を体験的に伝えることが重要でした。渡邊:私たちの身体を介して別の出来事を起こし、視覚障がい者との関係性をそこに作りだす。単純に情報を伝えるとか、共感するとは違ったことをしているのです。
伊藤:渡邊さんは「コミュニケーション」や「伝える」という言葉を避けようとしていたと思うのですが、それは非常に大切ですね。最初はスポーツと視覚障がい者の間をつなぐ、サポートするといった発想でしたが、伝えることから離れれば、視覚障がい者と晴眼者の関係は大きく変わる。実験では人を介すことで、ある種の変換や解釈が起き、別の出来事が発生していました。
渡邊:そうして作り出した出来事の中に視覚障がい者を巻き込むことで、スポーツを観戦してもらう。あえて名前を付けるとすれば、「生成的な観戦体験」(Generative Viewing)みたいな言い方になるでしょう。観戦といっても受け身ではなく、共同で何かをリアルタイムに生成するということです。