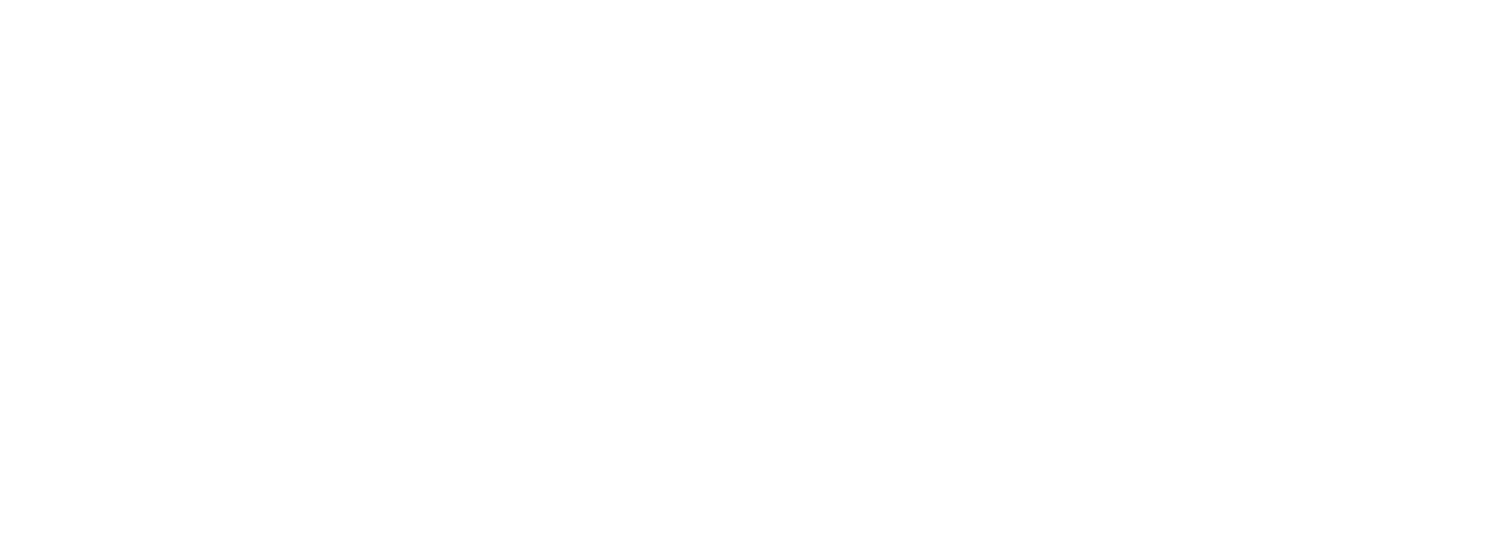

オリンピックや万国博覧会など、テレビなどのマスメディアが媒介し、視聴者に格別な連帯の感情をもたらす、大規模なメディアイベント。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控えた今、メディア論が専門の飯田 豊氏に、これまでの主なメディアイベントとその歴史的意義を、テクノロジーの変遷を軸に総括してもらいました。

飯田 豊
立命館大学産業社会学部 准教授。専門はメディア論、メディア技術史、文化社会学。著書に『テレビが見世物だったころ』(青弓社 2016年)、『現代メディア・イベント論』(共編著 勁草書房 2017年)、『メディア論』(共著 放送大学教育振興会2018年)など。
テクノロジーと共に変化するメディアイベントの形
私たちの日常生活は、都市に遍在するスクリーンから、手のひらの上のスマートフォンまで、さまざまなメディアに囲まれています。そのようなテクノロジー環境は、メディアイベントの受容経験を大きく変化させました。例えば、サッカーワールドカップでは現在、テレビの生中継を受動的に視聴するだけでなく、パブリックビューイングのような集団視聴が定着していますし、さらにはソーシャルメディアを通じて声援や野次がリアルタイムに拡散します。また、国際的なメディアイベントは、新しいテクノロジーにとって重要なデモンストレーションの機会でもあります。2016年、リオ五輪閉会式のフラッグハンドオーバーセレモニー(五輪旗の引き継ぎ式)における、ARをはじめとする映像演出は記憶に新しいでしょう。歴史をさかのぼれば、テクノロジーの革新とメディアイベントの変化との間には、とても密接な結びつきがあります。
メディアイベントとメディアアートの関わり
19世紀から20世紀半ばまでは、万国博覧会が国家間の技術競争にとって最大の舞台でした。そして万博が次第に、国家による「生産」の博覧会から、企業による「消費」の博覧会に変わっていったことに伴い、新しいテクノロジーを展示するための方法論として、アーティストによる芸術表現が取り入れられるようになりました。1970年の大阪万博で前衛的な映像技術が駆使されたことは、メディアアートの歴史を語る上でも避けて通ることができません。それに比べて近代オリンピックは、万博の余興として開催されていた時期もあるほどで、当初は大きなスポーツ大会ではありませんでした。大きな転機になったのは、ナチス政権下で開催された1936年のベルリン五輪です(別表参照)。そして戦後、オリンピックはテレビの普及に伴って、万博を凌駕する国際的イベントとして発展していきます。衛星中継によって放送ネットワークがさらに拡大すると、人々の意識を地球規模で動員していくイベントになりました。
このような状況が批判的に捉えられ、学術的に考察されていく中で、「メディアイベント」という概念が浮上してきました。同じ頃、マスコミュニケーションの手段としてのテレビを、個人による表現の手段に反転させようとするメディアアーティストたちが頭角を現します。'80年代、衛星中継をアーティストたちのコラボレーションの道具に転用する批評的な実験(=サテライトアート)を行なったナムジュン・パイクは、その第一人者と言えるでしょう。
メディアイベントの向かう先
現在では、テレビやネットの生中継を通じて感情を共有するようなメディア体験だけではなく、新しいテクノロジーに媒介された共時的な身体体験にも、再び大きな価値が見出される時代になっています。都市空間で行われるプロジェクションマッピングに多くの人々が集まるように、メディアアートとエンターテインメントの境界を揺さぶるようなプロジェクトが、さまざまな場所で展開されています。21世紀に入って開催された万博も、その例外ではありません。プロジェクションマッピングというテクノロジーを例にとっても、オリンピックの開会式における演出など、テレビなどで媒介されたメディアイベントとして存在感を発揮するとともに、共時的な身体体験を生み出す技術としても使用されています。このようにテクノロジーに着目してメディアイベントの歴史を見通す上では、メディアを通した視聴体験と共時的な身体体験を切り離して考えることはできないのです。
テレビを視聴することに比べて、ネットに媒介される価値や経験は多元的です。そんな中でメディアイベントは、さまざまな場所や状況に置かれている人々の注目を促します。多様なテクノロジーを横断し、相互に作用している影響関係を読み解いていくことが、今後のメディアイベント研究の役割と言えるでしょう。
Technology × Media Event の100年
| 1920 | アメリカで世界初のラジオ放送局KDKAが開局。 | |
| 1924 | パリ五輪 五輪史上、初めてのラジオ中継。 |
|
| 1925 | 日本でラジオ放送が開始。 | |
| 1926 | 社団法人日本放送協会が設立。 | |
| 1932 | ロサンゼルス五輪 ラジオによる生中継が認められず、日本から派遣されたアナウンサーは、取材メモを元にスタジオで競技を再現する「実感放送」を実施。 |
|
| 1936 | ベルリン五輪 ナチス政権下で開催され、壮大なスタジアムが建設される。近代五輪に「聖火」が復活し、聖火リレーや開会式がラジオで実況された。テレビの街頭放送も実現したが、フィルム撮影した映像を電送したため、生放送ではない。日本では、五輪初のラジオ実況中継を実施。新聞社が無線電送写真を導入。 |
|
| 1940 | 幻の東京五輪・日本万国博覧会 日中戦争の悪化に伴い1938年に開催権を返上。日本放送協会は五輪に向け、テレビの定時放送の実現を目指していた。 |
|
| 1948 | ロンドン五輪 五輪史上初のテレビ中継(ロンドン周辺のみ)。 |
|
| 1952 | 日本電信電話公社が設立。 | |
| 1953 | 日本でテレビ放送が開始。 | |
| 1959 | 皇太子御成婚パレード NHK、日本テレビ、ラジオ東京テレビジョン(KRT。現TBS)が中継。前年5月に100万件だったNHK受信契約が、御成婚1週間前の4月には200万件と倍増。 |
|
| 1964 | 東京五輪 五輪初の宇宙中継を実現。日本電信電話公社は、郵政省、NHK、KDDと共に、宇宙中継を実現するための研究開発に取り組んだ。また、五輪初のカラー放送が導入され、テレビの世帯普及率を押し上げた。 |
|
| 1967 | モントリオール万国博覧会 テレビが普及し、万博の存在意義が問われる中、マルチ・プロジェクションなどの映像技術が多用された。 |
|
| 1969 | 「アポロ11号」月面着陸がテレビで生中継される。 | |
| 1970 | 日本万国博覧会(大阪万博) 新聞やテレビによる報道を通じて参加が促され、「テレビ万博」とも呼ばれた。開会式中継は在阪民放4社にとって初の共同制作。日本電信電話公社は「電気通信館」において、東京と京都、種子島の特設会場からの中継映像を拡大投影したほか、開発中の「ワイヤレステレホン」の実演を行った。 |
|
| 1972 | 札幌冬季五輪 冬季五輪史上初めて、完全カラー放送が実現。 |
|
| 1984 | ロサンゼルス五輪 開催地の税金を投入しない代わりに、テレビ放映料、スポンサー協賛金が高騰し、「商業五輪」とも呼ばれた。開会式には、ジェット推進飛行装置を背負った「ロケットマン」が登場。 |
|
| 1985 | 国際科学技術博覧会(つくば万博) ソニーのパビリオン「ジャンボトロン」は当時、世界最大のテレビとしてギネス認定された。 |
|
| 1985 | 日本電信電話公社が民営化し、日本電信電話株式会社(NTT)が発足。 | |
| 1993 | 日本でインターネットが商用化される。 | |
| 1998 | 長野冬季五輪 開会式では世界五大陸を衛星中継で結び、小澤征爾による指揮のもと、ベートーベンの「歓喜の歌」を同時合唱。 |
|
| 2002 | 日韓共催サッカーW杯 メディアイベントの新しい受容形態として、パブリックビューイングが定着。 |
|
| 2005 | 日本国際博覧会(愛・地球博) インターネットや携帯電話の普及に伴い、参加者の間で情報の共有や交換が行われ、個人の万博体験が多様化。 |
|
| 2014 | ブラジルサッカーW杯 NTTが世界で初めて、グローバルIPを用いた8K映像伝送の実証実験を行い、NHKがパブリックビューイングを実施。 |
|
| 2016 | リオ五輪 開会式では、大規模なプロジェクションマッピングと連動したパフォーマンスが披露された。閉会式のフラッグハンドオーバーセレモニー(五輪旗の引き継ぎ式)では、斬新なCGやARを駆使した日本の演出が、国際的に高い評価を得た。 |
|
| 2020 | 東京五輪 |