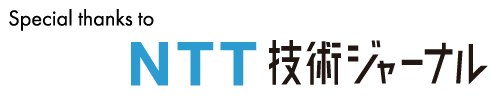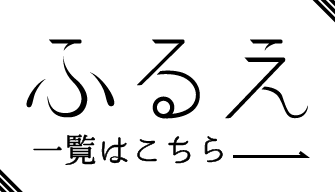触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌 ふるえ Vol.53
Sustainable Well-being
大いなる流れの中にあるウェルビーイング


大いなる流れの中にあるウェルビーイング
今号では、自然や生命とのつながり、時間を超えたつながりなど、より大きなものとの関わりから生まれるウェルビーイングについて取り上げます。人の生活との関わりから水の流れのシステムを捉える「流域」という考え方について村川友美氏に、マオリ族のよく生きるあり方につながる慣習「ティカンガ」について西尾 拡氏にそれぞれ話を聞きました。
人々の暮らしまで含めて水システムを捉える
「流域」という考え方

村川友美
Tomomi Murakawa
株式会社リバー・ヴィレッジ代表。九州大学工学部流域システム工学研究室から(株)リバー・ヴィレッジを設立。九州の山間地を中心に、水と人の暮らしの関係性を再構築する「地域のための小水力」に関する、調査、設計、建設マネージメント、地域づくりまで一連の業務を手がける。https://www.ri-vi.com/
小水力発電を手がける九州大学発のベンチャー企業
—村川さんが小水力発電事業に携わるようになった経緯を聞かせてください。
村川:リバー・ヴィレッジは、九州大学工学部の河川工学の研究室からスピンアウトしたベンチャー企業で、現在11年目になります。いわゆる河川工学というと、物理的な河川環境を対象とすることが多いですが、私が所属していた流域システム工学研究室は、「古来から、治水と利水が人間の暮らしの大元にあった」という担当教授の考えがあり、上流下流の人たちの暮らしまで含めて水のシステムを捉えて、研究していました。
そして、私たちが取り組む小水力発電[※]も、その考え方の延長線上にあるものなのです。人の営みと自然のあり方をどう適切に利活用しながら生きていくか、そこが小水力発電の最初の発想なんですね。昨今の水力発電は、再生可能エネルギーという文脈で語られることが多いのですが、そういったアプローチではなく、地域の人々の暮らし方の一つとして水資源を活用するという位置づけなのです。
私たちリバー・ヴィレッジという会社は、この小水力発電をコアにして、地域の人と対話し、地域を成り立たせる社会実装のための会社として立ち上がりました(写真1)。
※小水力発電:水の流量と落差によって発生するエネルギーを利用した水力発電の中で、一般的に出力1000kW以下のものをさす。河川や農業用水、上下水道などから直接取水することが多い。

[写真1] リバー・ヴィレッジが最初に手がけた大日止昴小水力発電所。宮崎県日之影町の大人(おおひと)集落の農業用水を活用した。稲作を優先し、非灌漑期のみ発電を行う。2017年11月に完成。
“流域”の中に生きているという実感
—“流域”についてもう少し教えてください。
村川:人や物の流れに川はとても大きな影響を与えています。例えば、下流に住む人は上流から木材を調達するとか、逆に上流に住む人は下流から塩を手に入れるなど、人間の暮らしには川を通じたやり取りがあり、文化圏もその中で形成されてきた部分があります。“流域”というのは非常に重要な「まとまり」だと考えています。
—そのような大きな流れに対する肌感覚、“流域実感”を私たちは持っているのでしょうか?
村川:以前うちに千葉県から学生さんがインターンシップに来たんです。それで、「川の始まりって見たことある?」と聞くと、大学4年生で千葉育ちのその子が「川に始まりがあるんですか!?」と言うんです。それで、川の始まり見に行ったんです。実際に水が湧きだしているところがあり、それが流れて支流になり、やがて本流になって大きな川になるわけですが、流域実感という言葉を聞いて、多くの現代人はそれを実感したことがないなと、本当に思いました。
—実感することは、行動に必要な要素だと思われますか?
村川:私たちは子ども向けに「水力発電とは何か?」という環境教育をやることがあります。電気は目に見えないものですが、水力の場合は流量×落差でエネルギー量が決まるので、触れようと思ったら触れられます。視覚的に見せるならば、例えば、黒部ダムの豪快な放水を見せて、これが何万kWのエネルギーになると説明します。一方で、打たせ湯のような流れを例に挙げて、「打たせ湯が肩に当たったら痛いよね。あの痛さがエネルギーなんだ」と言って、最初に物理を教えるんです。
これは大人に対しても同じで、水の力がエネルギーになって、物を動かし、発電するといった勉強会を最初に実施します。さらにフィールドに出て、取水するところから発電所まで見てもらい、水路に入った水が固まりとなって20数メートルの高さから落ちることを説明します。そういう話をすると、水力発電がとても身近になります。そして、それがどう電気に変わるのかというメカニズムが分かると、みんな意外とスムーズに取り組めるようになるんです。
流域の暮らしに直結する自らの手による水の管理
—水や自然との関わりを自分ごとにするには、どうすればよいのでしょうか?
村川:ひとつは、そこに住む人自身が水資源を活用・管理する手段を持つこと。具体的には、出力調整などの操作を含めて、自分たちの手で運用することですね。例えば、大雨の前は、水門を閉じるといった水管理の作業が必ず発生します。それを自分たちの手で行い、水を扱える機会が増えることで主体感が上がっていくのは、見ていて思います(写真2)。
水力発電をやるまでは、地域の水は田んぼと集落の防火用水に使っていましたが、田んぼをする人は減り、水を管理する人が減っていました。そこに水力発電が加わったことで、積極的に水を活用するという意欲が生まれ、かつて持っていた「水を使う」という文化を少し取り戻せたのかなと思います。
—「佐賀モデル」の成功例となった松隈小水力発電所にも尽力されてきました。
村川:佐賀県の山側の松隈地区が元気であることは、ひいては佐賀県全体の健全性を保つことになるのだと思います。例えば、山側に人がいなくなるとイノシシやシカなどの獣害も増え、侵食エリアが広がり、生態系のバランスが崩れていく。本当に上流に人がいなくなったとき果たしてどうなるのか、実際のところは分かりません。しかし、日本の国土の特性として、おそらく昔からそういうバランスがあったはずです。

[写真2] リバー・ヴィレッジが手がけたプロジェクトの一つ、佐賀県の松隈小水力発電所の取水口の設備。普段はメンテナンスがほとんど必要ないため実施頻度は少ないものの、豪雨などの影響で水量を調整したり土砂を除去したりする際には、地域の住民が直接水門のハンドルを操作する。
地域に入る際の住民との向き合い方
—小水力発電の提案などで地域に入っていくとき、どういうところに注意してアプローチしていきますか?
村川:それはよく聞かれるところです。ただ、そこを客観視するのはすごく難しいですね。私たちが一番最初に手がけたのは、宮崎県の日之影町という山深い場所にある大人(おおひと)集落でした。松隈と同様に過疎が進んでいて、着手から完成までは4年半ほどかかりました。今では収益もあってすごく前向きな地域になっていますが、最初の1年近くは賛否が分かれる状況でした。
—どのような意見があったのでしょうか?
村川:「そんなことよりも先にやらんといけんことがあるやろうが」とか、「借金背負ってまでやる必要があるんか」といった意見がたくさんありました。それが少しずつ変化していく過程がとても興味深かったです。
大人には2週間に1回程度の頻度で、片道4時間かけて通いました。一人ひとりと対話を繰り返し、何がみんなの心の奥底で引っかかっているのかをひもといていきました。私たちは「うんうん」と聞くだけですが、すると、誰かに聞いてもらったというだけで、何となく雰囲気が変わっていきます。私たちに対する信頼感が芽生えるのだと思います。
「進められるかどうかはまだ分からないけれど、どういう懸念があるのかは理解できました。その上で、考えられることからまずは始めてみましょう」といった具合に、スモールステップで検討を重ねていくことで、反対していた人も協力してくれるようになりました。
—小水力発電所を建設できたあと、地域の人は自立して運営していけるのでしょうか?
村川:その点は本当に重要です。今まで私たちは、ほかの県も含めて2年に1回ぐらいのペースで建設を進めてきました。どこも同じプロセスで入りますが、いずれも私たちの手を離れて、自立して運営されています。
担当教授からいつも言われていたのが「水は最後に残されたコモンズだ」という言葉です。誰のものでもないけれど、誰でも使わないといけないものだから、ここを入口にして、地域資源を語ることで、地域の人たちが、自分たちが取り組まなければ、という覚悟みたいなものが生まれるのではないかと感じています。
松隈小水力発電所




松隈小水力発電所の設備。発電所は3.6×2.5mの小さなコンテナ型で設備もパッケージ化されており、設置のコストが低く押さえられている点も大きな特徴。
発行日 2024年7月1日
発 行 日本電信電話株式会社
編集長 渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)
編 集 矢野裕彦(TEXTEDIT)
デザイン 楯まさみ(Side)