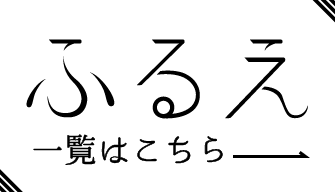触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌 ふるえ Vol.57
Sustainable Well-being
スポーツへのウェルビーイング (e)スポーツからのウェルビーイング
スポーツとウェルビーイングの関わり方にはさまざまなかたちがあります。頂点をめざすアスリートのためのウェルビーイングとeスポーツを通して子どもたちに学びを提供する取り組みに注目しました。
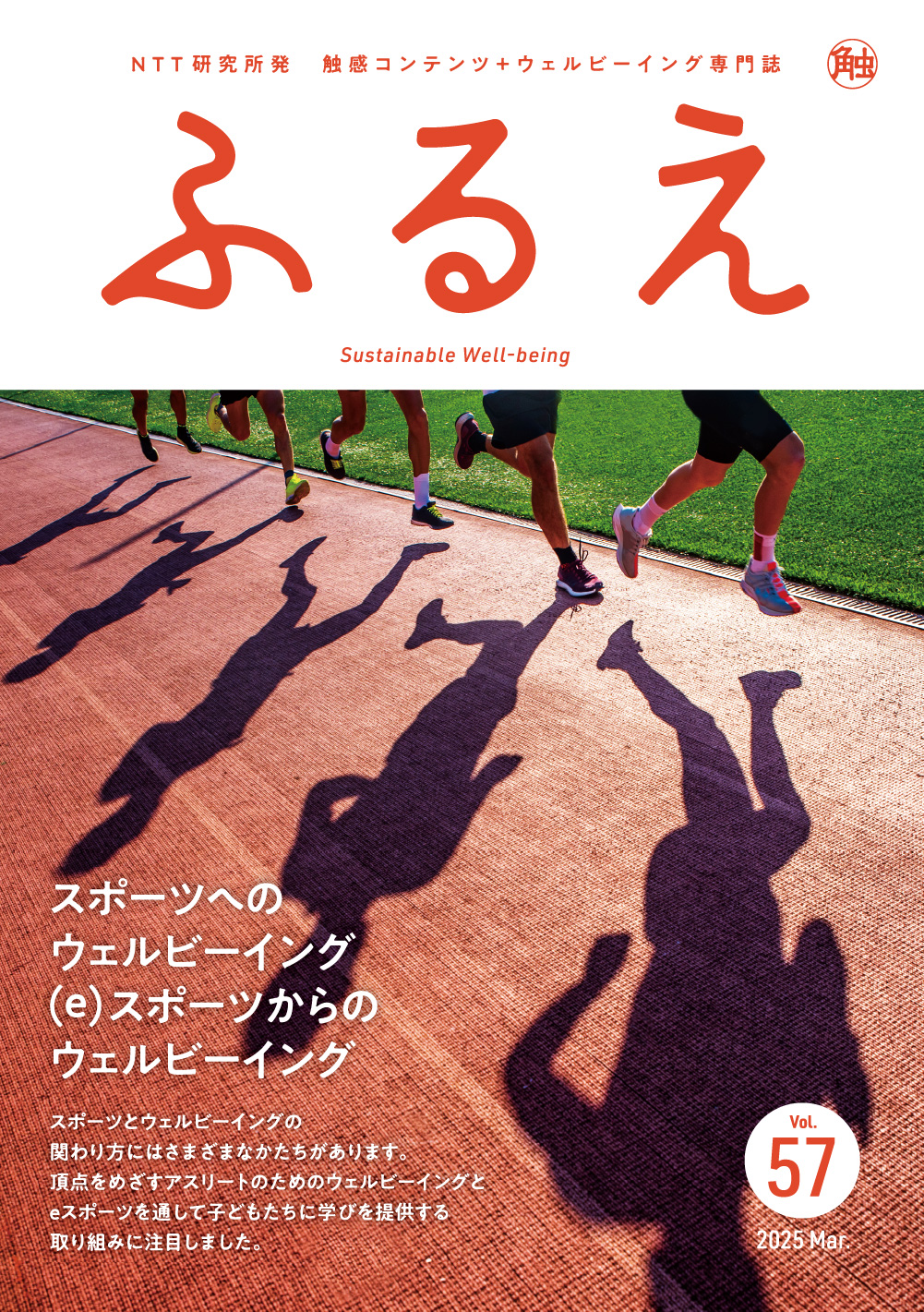
ウェルビーイングの視点からトップアスリートを支える

衣笠泰介
Taisuke Kinugasa
独立行政法人日本スポーツ振興センター ハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)/国立スポーツ科学センター スポーツ科学研究部門主任研究員。スポーツ科学者/パスウェイサイエンティストとして、HPSCでは競技別トータルコンディショニングに関する研究と支援、アスリート・ウェルビーイングに関する研究などを行う。
トップアスリートのウェルビーイング
—衣笠さんがアスリート・ウェルビーイングの研究に関わることになったきっかけについて教えてください。
衣笠泰介(以下、衣笠):もともと私はスポーツ生理学を専門分野とし、アスリートのコンディショニングの研究をしていました。オーストラリアに留学してトップアスリートのコンディショニングの研究に注力し、その後、シンガポールでジュニアアスリートや競泳の代表チームなどを支援していました。そこでは「パフォーマンス向上」が常に求められ、アスリートはその目標に向けて集中して取り組んでいました。しかし、その一方で、海外の調査ではトップアスリートにケガやオーバートレーニングなどの問題が表面化していることが分かってきました。
そんな背景の中、所属するハイパフォーマンススポーツセンター(以下、HPSC)から、ウェルビーイング(以下、WB)に関する研究をやってみないかと声をかけていただき、アスリートのWBに焦点を当てた研究を始めることになりました。WBという言葉は、海外ではよく耳にしていましたが、日本におけるその実態についてはよく分からない状況でした。しかし、研究を進めていく中で日本の実情を知り、それを深く理解するにつれて、WBの重要性をますます感じるようになりました。
—HPSCとは、どのようなところなのでしょうか?
衣笠:HPSCは、国際競技力向上を目的とする中核拠点として、2016年に日本スポーツ振興センターによって設立されました。これは、オリンピック競技とパラリンピック競技のトレーニング施設である味の素ナショナルトレーニングセンターと、医・科学、情報の研究施設である国立スポーツ科学センターを併せ持つ、トップアスリートを支援する組織です。トップアスリートの競技成績は、ほんのわずかな差で勝敗が決まります。そのため、現在ではコーチとアスリートの日々のトレーニングに加え、スポーツ科学の活用が進んでいます。それは大会前の準備期間だけでなく、大会期間中も含めてです。
一方で、アスリートがパフォーマンスを向上させていく代償として、アスリートの健康問題が課題の一つとして挙がっています。HPSCでは、パフォーマンスの向上とアスリートの健康を両立させるため、WBの向上に向けた包括的な支援のあり方を検討しています。
—WBの研究を始められたのは、いつごろですか?
衣笠:2018~2019年くらいだと思います。2018年には、国際オリンピック委員会(IOC)が「アスリートの権利と責任の宣言(The IOC Athletes’ Rights and Responsibilities Declaration)」を採択しています。その中には、「アスリートの権利として、メンタルヘルスやフィジカルヘルスが護られる」というくだりがあります。当時、海外のいくつかの国では、スポーツ統括機関がアスリートのWBの支援に先進的に取り組み始めていました。
例えば、ニュージーランドのラグビー代表「オールブラックス」では、チームとしてWBやメンタルヘルスを支援する専門家を複数名配置し、ニュージーランド全土でラグビー代表選手を支援する体制を整備していました。その取り組みを統括しているネイサン・プライス博士(Nathan Price、当時 New Zealand Rugby Education & Wellbeing Manager)を2019年にHPSCで招待し、アスリートのキャリアセミナーで講演していただきました。その後、HPSCも本格的にWBの研究をスタートしました。
当時の日本は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、トップアスリートへの支援に国費が投入されてプレッシャーが高まる状況でした。また新型コロナウイルスの蔓延によって、アスリートのメンタルヘルスに関する課題が表面化し、その重要性が一層浮き彫りになりました。こうした中で、日本におけるアスリートのWBに関する研究と支援の必要性が急速に高まったのです。
—衣笠さんは、どのようなアプローチで研究に取り組まれたのでしょうか?
衣笠:アスリートのWBは明確な定義が定まっておらず、メンタルヘルスに関しても臨床的な概念が中心で、アスリートにおけるWBやメンタルヘルスをどう定義し、定量化するかを明確にする必要がありました。そこで、まず日本でのトップアスリートのWBの実態や、アスリートが所属している中央競技団体でどのような支援が行われているかを把握するため、文献レビュー、アンケート調査を実施しました。これらの調査結果によってエビデンスに基づいた包括的な支援体制が構築できるのではないかという仮説が立ちました。
その研究成果をまとめたレビュー論文[※]では、学術やビジネスでのWB、世界保健機関(WHO)の健康の概念などを整理し、海外有識者の意見も踏まえた上で、アスリート・ウェルビーイングを「アスリートの身体的・精神的・社会的幸福感が相互に作用した状態である」と定義しました。さらに、キャリアの問題、財政的な支援や法的な保障にも配慮が必要であるとしました。また、アスリートにおけるメンタルヘルスについては「健全な精神的健康から病的な精神疾患までの一つの連続体として捉えられる」としています。
アスリート・ウェルビーイングを支援するために
—現状のトップアスリートのWBには、どのような課題があるのでしょうか?
衣笠:アスリート・ウェルビーイングを身体的、精神的、社会的な側面だけでなく、組織的、教育的、経済的、法的といった多面的な側面から捉えると、トップアスリートが直面する課題は非常に多岐にわたっていることが分かります(図1)。例えば、トレーニングのし過ぎでケガをしたり、精神的に不健康になったり、周囲からのプレッシャーや引退後のキャリアに関する悩みなどもあります。また、スポンサーが獲得できずに競技生活の継続が困難になるケースもあるでしょう。さらに、最近ではSNSでの誹謗中傷の問題もあります。
アスリートのウェルビーイング

図1 アスリート・ウェルビーイングの概念。競技生活を支えるには、アスリートのウェルビーイングを競技に直接関係するような身体的、精神的といった側面だけでなく、経済や法律といった多様な側面から捉える必要がある。
先ほどの論文では、アスリート・ウェルビーイングの支援体制について「アスリートのライフスタイルを習得するプログラムやデュアルキャリア教育を含めた、包括的な支援機能が求められている」と提言しています。アスリートのWBと健康を高めていくためには、身体に関する生理学的な支援だけでなく、メンタルトレーニングの専門家、臨床心理士や精神科医、さらには社会的、教育的、経済的、法的な専門家も含めた支援体制を作っていく必要があります。HPSCでは、アスリートを真ん中において、いろいろな専門家が協力・協調して連携を組み包括的に支援していく「トータルコンディショニング」という概念を提唱しています(図2)。
そして、アスリートの“人としての人生”を見ると、引退したあとのWBも考えていくことになります。そのためにも、パフォーマンスの向上だけでなく、現役のときからWBの向上についてアスリートが考えられるように、支える側がきっかけを作ることは重要です。アスリート生活のあとに続く長い人生のWBを、自ら考えていけるマインドを持ったアスリートを育てていくためには、幼少期からそういったメンタリティを備えていく必要があります。もちろんHPSCの支援だけでなく、さまざまな研究機関、あるいは大学の先生方と連携しながら、地域も含めてこうした支援体制を国全体で作っていく必要があると思っています。
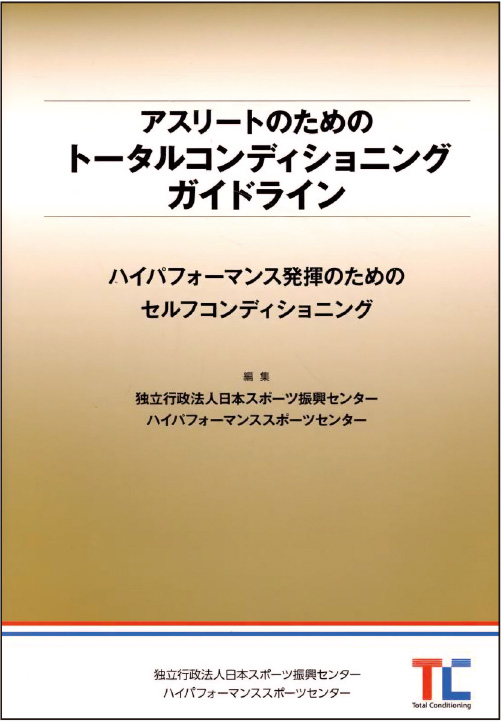
図2 『アスリートのためのトータルコンディショニングガイドライン』。日本スポーツ振興センターと大塚ホールディングスによる国際競技力向上を図るためのコンディショニングの研究プロジェクト「Total Conditioning Research Project」で得られた成果などを元に、アスリートのハイパフォーマンス発揮のためのセルフコンディショニングの知見や方法をまとめたガイドライン。
—幼少期の教育から引退後のことまで含めると、社会全体での取り組みになっていきますね。
衣笠:トップアスリートに「どのような人に支えられてきたか?」というアンケート調査を行ったところ、幼少期から成人期にわたって保護者が常に上位に挙げられていました。保護者はアスリートの個人的な背景も含めて理解している存在であり、指導者やコーチもそういう背景を踏まえてパフォーマンスの向上に取り組む必要があります。また、トップアスリートであればあるほど、スポンサーやほかの関係団体も含めて関係性が複雑になりがちです。
そのため、アスリート自身が周囲との関係性や支援の仕組みを理解することが重要です。そうした視点が欠けていると、ビジネス上で不当に扱われたり、望まないかたちで権利が利用されたりするリスクが生じる可能性があります。もちろん、アスリートが多くの関係者に支えられていることを認識して感謝の気持ちを持つことは、モチベーションの向上だけでなく、人としての成長につながる可能性もあります。
—アスリートのWB向上に向けた、今後の考え方について教えてください。
衣笠:われわれも研究に取り組み始めてまだ数年ですし、社会全体で取り組むものでもあるので、今の活動を継続し、これからも賛同者や理解者を増やしていくことが大事になると考えています。ただし、ハイパフォーマンスの世界は非常に厳しいもので、トップアスリートは10年以上の育成過程を経て、身体的にも精神的にも成長し、卓越した能力を身に付ける、特別な環境にいます。その意味でも、それぞれのアスリートがどのような環境で、保護者、指導者の下で育ってきたのかということも把握しながらアスリート・ウェルビーイングの支援のあり方を考えていく必要があると思います。
もちろん、アスリート・ウェルビーイングを、アスリート自身だけでなくコーチや支援スタッフといった支える側も含めてしっかりと根付かせるためには、実態を示すエビデンスに基づいた包括的な支援をしていくことが重要になってくると思います。また、アスリートの考え方を変えるには、アスリート同士が自然とそういう会話を交わすような環境を作るのが最も効果的だと思います。教育を通して幼少期からアスリート・ウェルビーイングの考え方に触れる機会を設ければ、トップアスリートとしてその競技の最高レベルに達したときに、新たな文化が自ずと生まれてくるのではないかと感じています。

発行日 2025年3月1日
発 行 日本電信電話株式会社
編集長 渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)
編 集 矢野裕彦(TEXTEDIT)
デザイン 楯まさみ(Side)