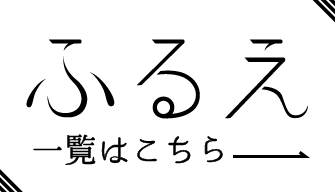「モア・ザン・ヒューマン」との持続的なウェルビーイングを実現するために
サステナブルウェルビーイング社会連携講座キックオフシンポジウム
「人間・情報・自然が つながりあう社会に向けて」
2025.3.10 /東京大学 情報学環・福武ホール
国立大学法人東京大学は、日本電信電話株式会社(以下、NTT)と共に、東京大学大学院情報学環に「サステナブルウェルビーイング社会連携講座」を開設しました。同講座のコンセプトと、キックオフシンポジウムの模様を紹介します。

東京大学において「サステナブルウェルビーイング社会連携講座」がスタートしました。本講座は、アートやデザインなど表現領域を含む情報学の実践的研究・教育を進める東京大学大学院情報学環と、幅広いICTの基礎研究から実社会における価値を創出するNTTが連携し、現代の社会課題に向き合う、サステナビリティとウェルビーイングを接合する先進的かつ包括的なフレームワークの構築に取り組むものとなっています。
同講座には、アートやデザイン、コミュニティ、無線通信、センシングのほか、回遊魚からコンピューターセキュリティまで、多様なジャンルの研究者が参画しています。そして、複数領域の専門家がそれぞれの専門を持ち寄るインターディシプリナリー(Inter-disciplinary)スタイルの協働ではなく、トランスディシプリナリティー(Trans-disciplinarity)と呼ばれる、双方が越境して絡まり合いながらジャンルを形成しくことをめざしています。
3月10日には、そのキックオフシンポジウムが実施されました。前半の第一部では、情報学環の目黒公郎 教授(学環長)とNTTの木下真吾 執行役員(研究企画部門長)から設立あいさつがあり、講座設立の背景と概要について、東京大学で本講座の主担当を務める筧 康明 教授とNTTの渡邊淳司 上席特別研究員(本誌編集長)から説明がありました(写真1)。
後半の第二部では、①《自然》(と)のウェルビーイング、②《モア・ザン・ヒューマン》と関わりあう、③持続可能なエコノミーとコミュニティ、という3つのテーマで、参加メンバーによるプレゼンと、それぞれのテーマに関する対話が行われました(写真2)。
人間と動植物など、人間とは異なる時間軸を持ったものとのウェルビーイングや持続可能性を考えるには、その時間軸の違いを考慮する必要があります。また、その広がりは自然生態系に限らず、AIやロボット、コンピューターウイルスなどの情報技術による存在まで含むこともできます。本講座では、そのような人間とは異なる存在一般を「モア・ザン・ヒューマン(More than Human)」と捉え、持続可能なかたちで、それらと共によく生きるための関わり方を探求します。
本講座は、2027年11月までの3年間にわたって開設され、一般にも開いたかたちで実施されます。

写真1 東京大学の主担当である筧 康明 教授から、テクノロジーと自然環境の両方を見つめ、人としての視点を乗り越えて考えるための「モア・ザン・ヒューマン」というキーワードについて説明がありました。

写真2 回遊魚の研究を専門とする東京大学の黒木真理 准教授と、環境センシングによる研究を行っているNTTの岸野泰恵さんによる対話の様子。講座には、東京大学、NTTの双方からさまざまなジャンルの研究者が参加します。