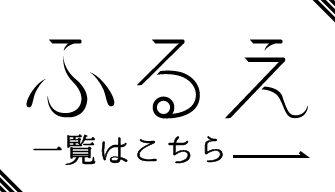自己や他者と向き合うための身体的なライフスキル

柏野 牧夫
Makio Kashino
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 フェロー。専門は心理物理学・認知神経科学。特に聴知覚、多感覚相互作用、感覚運動相互作用、コミュニケーションなどについて、無自覚のうちに柔軟で巧妙な情報処理を実現する機能的・神経的メカニズムの解明に従事。近年は、発達障がい者やアスリートなどにも研究対象を広げ、脳・身体・環境の動的相互作用の観点から認知の多様性と可塑性を研究。
アスリートの潜在的な脳の機能をひもとく
—ご自身の研究や活動について聞かせてください。
柏野牧夫(以下、柏野): 元々は認知神経科学の領域で聴覚を専門に研究をしていました。近年は、さまざまなご縁もあって、スポーツ系の研究が増えています。ただ、スポーツと言っても、筋肉を鍛えるとか、フォームの研究といった、いわゆるスポーツ科学ではなく、スポーツの研究の前から私たちがテーマの一つにしていた「潜在」、本人の意識から隠れているものをテーマにしています。つまり、脳あるいは身体でいろいろなことが起きているけれども、意識にはほとんど上っていない。その部分をひもといていくということをやっています。
—具体的な例を挙げていただけますか?
柏野: 例えば、プロ野球選手の目の使い方ですね。「打つときに、ボールをどう見ていますか?」と聞いて、その様子を答えられる選手はいるのですが、実際に目の動きを解析してみると、その答えの通りにはなっていないのです。150km/hで動くボールでも、それに目が滑らかに追随していれば、相対速度は網膜上ではゼロで、細部まで捉えることができます。ただ、ある地点から少しだけ目が先回りを始めるんです。ボールにコンタクトする直前には、予測される点に視線を移していることが分かりました。一方で、先回りし始めた瞬間から脳は情報を失います。この滑らかな視線の追随から先回りし始めるタイミングによって、バッターのレベルが変わってきます。タイミングが0.1秒違えばボールの位置は4~5m違うわけです。その4~5mの情報を捨ててしまう人と、脳が処理して反応できるギリギリのところまで使える人に分かれます。
—解析した結果をフィードバックすることで、選手の動きが変化するというような経験はありますか?
柏野: いろいろあります。前提として、私たちはその競技の専門家ではありませんから、頭ごなしに「こうした方がいいですよ」とは言わないようにしています。また、そもそも制御できない無自覚なプロセスを意識することが、よい結果を生むとも限りません。とはいえ、やはり変わることはあります。例えば、先ほど話したプロ野球選手の目の使い方について、ある選手にフィードバックしたところ、1年ほどで劇的に変わりました。われわれはただ理屈を説明して、「あなたはこうなっていますが、それがこうなると、こういうメリットがあります」といった話をしただけです。あとは本人が理解して、自分がどうするべきか考えたのだと思います。結果的に打率は上がり、ホームランも増えました。
身体的なスキルは人と人との関わり方にもつながる
—柏野さんがトップアスリートを対象に研究されていることは、一般の人々にも生かせるものでしょうか?
柏野: われわれもトップアスリートだけでなく、もっと多くの人に役立つものにしたいと思っています。気づいていないけれど、日々のパフォーマンスに劇的に影響するような身体的な要素があります。物を持ち上げるときに、こうすると楽に持ち上がるけど、こうすると腰を痛めますといったようなことは、日常の身体動作の中にもありますよね。そのような身体的なスキルを身に付けられることはあると思います。
—自分との向き合い方みたいなものが変わっていく身体的なファクターとして、何を意識したらよいと思いますか?
柏野: 難しい質問ですね。まず、「立ち方」はとても重要です。例えば、プロ野球選手でも立ち方をすごく意識している選手がいます。ちゃんと立てているときは、ちゃんと投げられる。それから「呼吸」。動作のときに、どのタイミングで吸って、どのタイミングで吐くかみたいなものは、デタラメにはできません。しゃべるときは、息を吸いながらではなく、吐きながらしゃべりますよね。しゃべれるということは、その方法を会得しているということです。
もう少しスキル寄りだと、「重心」をどうコントロールするかですね。併せて、どこに力を入れてどこの力を抜くかといった「バランス」感覚は、いろいろな動作に共通して大事なところ。それをうまくすれば楽に大きい力が出せたり、逆にものすごくがんばっているのに実を結ばなかったりします。
—呼吸やバランスは、メンタルの話とも関わるところなのでしょうか?
柏野: 例えば、緊張した状態では、何かがズレたり、余計な力が入ったり、脱力しておくべきなのに力が抜けないといったことが起こります。そういう意味では、確かに関係はあると思います。それだけではなく、瞬間的な動きでは、自分というもののバウンダリー(境界)がよく分からなくなるんです。柔道でも、技が非常にきれいに決まったとき、どっちが投げているのか分からないときがありますよね。それはもはや共同作業です。相手と一体化した動作というか。
—重心やタイミングというのは、自分だけでなく人との関わりでも言えるような気がしてきました。
柏野: そうですね。例えば、相手が技をかける前に逆側に重心が傾くといった一瞬の動きを素早く捉える。それを察知するのも能力だと思います。人と人とのコミュニケーションでも、相づちのタイミングがワンテンポ遅れるだけで、「え?」となったり、行き違いがあるのかと不安に感じたりしてしまう。同じ動作をしても、タイミングがズレただけでおかしいと思えてしまう。アイコンタクトもそうですね。普通の目配せであれば、適度なタイミングで目を合わせたりそらしたりするものであって、凝視することはありません。私の場合、何を言うかより、どう反応するかという、身体的な部分の方にコミュニケーションの本質があるように思います。
身体を動かすことの本質を求めて
—何かを察知して適切に反応する。何をすればそういう力が付くのでしょうか?
柏野: それは、分かりません。ただ、一つには経験ということがあるのではないでしょうか。子ども向けのスポーツ教室の人に最近聞いたのですが、以前なら当たり前にできるはずだと思っていたことができない子どもが増えてきた、という印象があるそうです。ボールを軽く投げて、受け取ってみようと言われても、取れずに顔に当たってから手を叩くみたいな。それは、こうやったら痛い目に遭う、でもこうしたらうまくいく。そういう経験がないために、やってみようと言われても反応できないわけです。逆に、多くを経験し、身体の使い方の達人となっているトップアスリートに、そういう能力をどうやって身に付けたのかと聞いても、それは普通の人にどうやって歩けるようになったのか聞くのと同じで、考えたこともないのではないでしょうか。
—重心の移動や呼吸といった視点を、コミュニケーションにおける資質・能力(コンピテンシー)として身に付けることができれば応用できそうに思えます。
柏野: 特定の競技のスキルではなく、もっとベーシックな要素として、学校の体育の授業などを利用して、ある時期までに身に付けられれば、そのあとどんな競技や運動にもそれなりに適応できるということはあるかもしれません。ただ、現在の情報技術などは、その逆の方向に振れているとも感じています。
実は、昨年の11月頃から、腰の神経障害で歩くことに困難を抱えるようになりました。それまでは毎日野球をしたりして動けていたのが、腰を痛めてからものの2週間もしないうちに、股関節が意のままに動かなくなってしまったのです。動けないわけではなく、無自覚的な動作に制限が加わった状態ですが、自己効力感が著しく低下し、ウェルビーイングに大きく影響します。今、この状態を少しでもよくするにはどうすればよいのか、動くことの本質は何だろうといったところに、もう一度、向き合っているように思います。例えば、自分にとって「歩く」ということ一つ取っても、姿勢だったり重心だったり、よりベーシックな無自覚的な膨大な動作に基づいているという感覚があります。
そして、このような不自由さ(ルール)の中で、少しでもうまく動けるようになろうとする行為は、ある意味「スポーツ」です。制限の中でうまくなろうとするチャレンジは、それまでやっていた野球と何ら変わらないというのが実感です。実際、だいぶ上達(回復)してきていますから。

写真 アスリートに協力してもらっての実験の様子。野球のバッティング中の視線と身体の挙動の測定(左)と、スノーボードビッグエアの大会決勝の試技直前の脳波計測(右)。本番、もしくはそれに準じる状況で、トップアスリートの生体信号や身体の挙動を多角的に計測する。