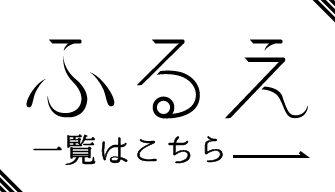触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌 ふるえ Vol.60
Sustainable Well-being
心と体のライフスキル
目の前の人を気にかけ、苦しみや悲しみを分かち合う。そんな人の心を察知して反応する力は、本来、誰もが持つものですが、すぐに発揮できるわけではありません。そういったコミュニケーションの資質・能力は身体の感受性や応答力が基盤にあるのかもしれません。
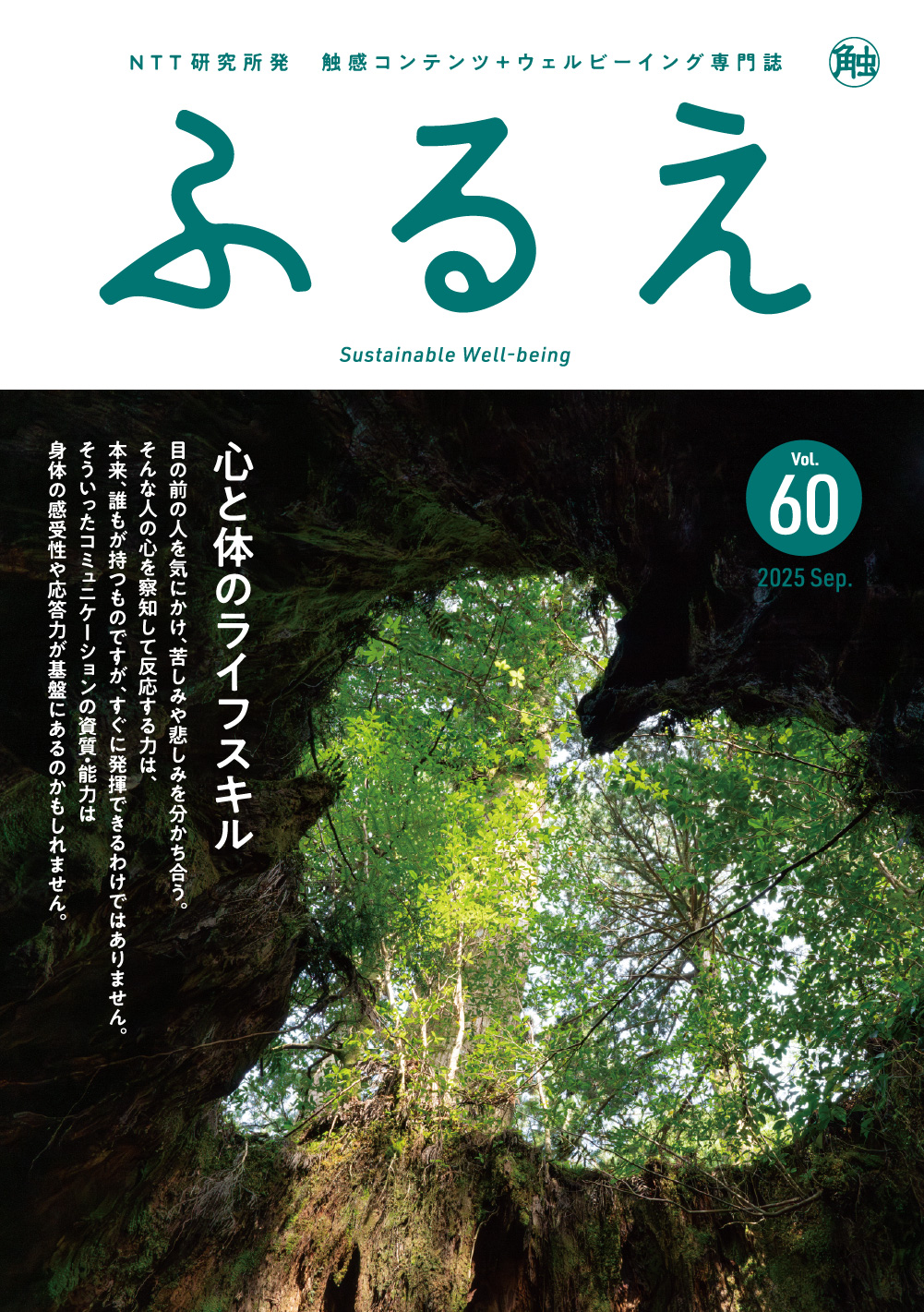
誰もが持つケアの力を発揮
コンパッション・コミュニティ

堀田 聰子
Satoko Hotta
慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科 教授(認知症未来共創ハブ代表)。学生時代から自立生活を送る障がいのある方の介助などに携わり、人と地域がもともと持つ力の回復・再生の手がかりを探りながら対話と活動を続ける。博士(国際公共政策)。
個人とコミュニティの応答性を高める
—まず、堀田さんのご活動について教えてください。
堀田聰子(以下、堀田): 主に担い手の観点から、人間的で持続可能なケアと地域づくりに向けた移行の支援や加速に取り組んでいます。小、中学生のころから障がいのある方の日常生活の介助、外出や旅行の企画・同行を始め、現在も続けています(写真1)。大学時代には、ヘルパー資格を取得し、ヒッチハイクで全国47都道府県を踏破しました。車から降りたところで近隣の福祉施設を探し、お手伝いする代わりに泊めていただくこともありました。こうした中から、ケアに関わる専門職や事業者、利用者、家族、自治体、研究者、まちづくりに携わる方々、学生、デザイナーなど、さまざまな人たちと活動するようになりました。

写真1 学生時代に障がいのある方と企画した旅行先で(後列右)。当たり前の暮らしの幸せをあきらめずに行動を起こす当事者たちから多くを学んだ。
—学生時代から多くの現場に入られてきたのですね。
堀田: はい。今も現場に軸足を置き続けたいと考えています。当事者が抱える苦悩や苦しみに呼応して、自分の気持ちや考えを整理することに始まり、他者と対話を繰り返し、その結果として、共に行動を起こしていく過程を大切にしたいからです。個人だけでなく、コミュニティも、関係機関も応答性を高めることが重要で、現場と政策、研究に橋を架けたいというスタンスで活動してきました。
地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合うケアリングコミュニティについて研究する過程で、注目するようになったのが、「コンパッション(Compassion)」に支えられたコミュニティという考え方です。
コンパッションに支えられた地域共生社会
—「コンパッション・コミュニティ」の考え方について教えてください。
堀田: ケアの医療化と専門職化、専門職ケアの提供を保障する制度の整備が進む中、コンパッションの働きによって、生老病死を地域住民の手に取り戻そうという考え方です。死にゆくこと(Dying)、死(Death)、喪失(Loss)は、すべての人にとって避けられない自分ごとです。死や喪失など、グリーフに共同で応答することで、互いに支え合うよりどころが築かれるというわけです。
「エンド・オブ・ライフケア」は、専門職だけでなく、すべての人の責任ということが前提になる概念でもありますが、ここで「エンド・オブ・ライフ」を、人生の終末期という意味合いだけでなく、アイデンティティや帰属の喪失・終結も含めた言葉として捉えていることも、とても意義深いと思いました。
実際に世界各国で社会的な行動が広がっており、足を運んでみると、国内で生まれてきている動きにも通じると感じられ、まずは基本書である『コンパッション都市(Compassionate Cities)』の翻訳に取りかかりました(写真2)。
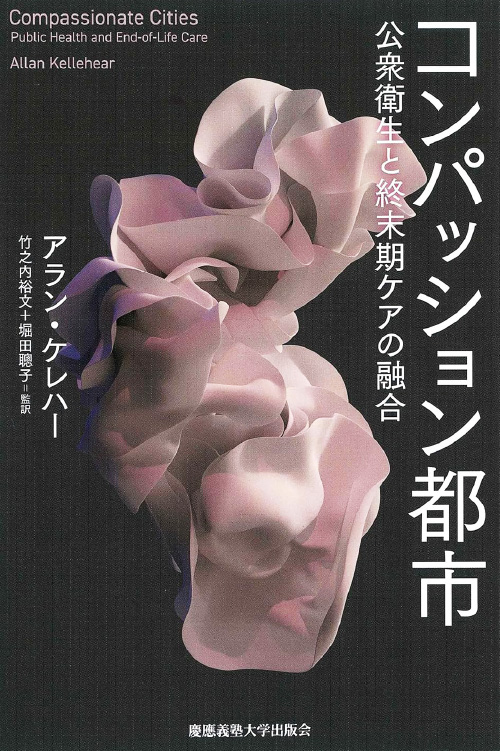
『コンパッション都市:公衆衛生と終末期ケアの融合』 アラン・ケレハー 著 竹之内裕文/堀田聰子 監訳(2022・慶應義塾大学出版会)
写真2 コンパッション都市・コミュニティ運動のパイオニアである著者のアラン・ケレハー氏は、日本と縁が深く、2026年1月にも来日が予定されている。
—「コンパッション」を日本語にするのは難しかったのではないでしょうか?
堀田: これまでコンパッション都市・コミュニティの訳語として、「共感都市」や「慈悲共同体」が提案されてきました。共感はコンパッションを構成する要素であること、慈悲もコンパッションの一面を捉えているものの、特定の宗教と結び付くこと、さらに語義に忠実に「共苦」などの候補も浮かびましたが、結局、「コンパッション」とニュートラルな表記にしました。コンパッション都市・コミュニティの提唱者であるアラン・ケレハー教授は、コンパッションを「他者の苦難や苦悩に突き動かされる人間的な応答、柔らかな反応」と説明します。他者と苦しみを分かち合い、その苦しみからの解放を願って具体的な行動が生み出されるということです。苦しんでいる人がいたら放っておけない、何かせずにはいられないといったことは、皆さんも経験があるのではないでしょうか。
一方で、コンパッションは誰にでも備わっていますが、十分起動できていないのではないか、それを発揮するためには一定のスキルも必要ではないかと考えています。また、発揮することを抑制されているという面もあります。例えば、私は訪問介護のヘルパーとして活動することがありますが、同居するご家族の食事の用意や洗濯など、利用者本人以外のための家事は、介護保険のサービス対象として認められていません。さまざまなルールや慣習などが、妨げになっている部分もあると思います。みんなが持っているはずのコンパッションを発揮できる環境を整えていくことは、とても大切なことで、そのためにできることは多いと感じています。
ライフスキルとして身に付けるコンパッション
—コミュニティの中でのインフォーマルな支え合いとフォーマルな支援のバランスは、どのように捉えているのでしょうか?
堀田: ケレハー教授は「95%ルール」を強調しています。エンド・オブ・ライフケアにおいて、医療や介護等の専門職が目の前にいる時間は全体の5%程度に過ぎない。残りの95%は家族や友だち、近所の人たち、もしかしたらペットやテレビ、インターネットなどと共にある。もちろん、5%のところにひも付くフォーマルな制度や仕組み、専門職ケアも重要ですが、95%を占めるコミュニティ、インフォーマルな支え合いに関わる人々が"準備ができた状態"であることが不可欠です。
—“準備を整える”ためには、どうやってスキルを身に付ければよいのでしょうか?
堀田: コンパッション・コミュニティの先進地の一つと言われるインドのケララ州では、30年以上にわたって、ケララモデル[*1]と呼ばれる地域密着で住民主体のケアモデルが構築されています。例えば、Institute of Palliative Medicine(IPM)[*2]では、専門職向けの研修に加え、広く住民向けに啓発プログラム(1時間)、入門研修(3時間)、それにケアラー研修(20時間)を長年続けています。特に学生たちがこの輪をどんどん広げていて、視察メンバーがゲームセンターで出会った地元の若者もIPMの活動を知っていて、「困ったときに助け合うのは当然」と言われたそうです。IPMで学生たちと話すと、「ここは自分たちの場所」「仲間がいて楽しい」「以前は困っている人がいてもどうしてよいか分からなかったが、今なら分かる」と目を輝かせていたのも印象的でした(写真3)。でも、研修を受けたからといって活動することが必須ではない。いずれ必要となるライフスキルとして、できるだけ多くの人が備えておくべきという発想なのです。

写真3 インドのケララ州にあるInstitute of Palliative Medicine(IPM)で現地の学生たちと(後列右)。3度目となる2025年3月の訪問では、国内の医療介護福祉関係者や大学教員など約20人を引率した。
—ケアラー研修ではどのようなことを行うのですか?
堀田: IPMは、国内外の緩和ケア・長期ケアのキャパシティビルディングに関わるWHOの協働センターでもあり、さまざまな困難を抱える個人のウェルビーイングの改善を助けるケアラー向けに、WHOのガイドラインに即して、独自に教材や研修を開発しています。知識や技術を一方的に教え込むというものではなく、具体的な事例から考え、対話する、民主的な学びが展開されます。例えば、「緩和ケアって何?(What is Palliative Care?)」という章は、次のような事例から始まります。
進行した乳がんを患う32歳の女性がいます。彼女は夫と8歳と6歳の子と暮らしています。主治医は、夫に彼女の余命は6~9カ月くらいと告げています。
あなたが昨日彼女を訪ねたところ、彼女は全身の痛みを訴え、とても不安そうでした。
これに対し、何に困っているか、何を願っているか、あなたがご近所だったら何ができるか、個人で、グループで考え、共有します。その上で、緩和ケアの定義、身体のことだけでなく、心のことや社会的、経済的なこと、スピリチュアルな苦しみもあり、ご家族にも苦悩がある、ということを学んでアイデアを見直す。次は行動に移そうとなると、仲間はどうやって見つければいいんだろうか──と考えを深め、コミュニケーションや身体介護の基礎的なスキルも身に付けられるようになっています。
日本の大学で、この事例をそのまま出したところ、「そもそも近所のご家庭の事情なんて、分からないですよね」から始まり、最初は「もし分かったとして、医療の専門家じゃないので、できることはありません」といった反応でした。でも、グループワークで「実はうちの母親が癌の末期で」「自分はヤングケアラーだった」と話し出す学生が出てきて、実は身近なこと、“自分たちごと”でもあることが実感され、「こんなことが助かった」「これがあったらよかった」と議論が尽きませんでした。
—今後の方向性について教えてください。
堀田: コンパッション・コミュニティへの共鳴は国内でも広がりつつあり、いくつかの地域や学校で、コンパッションに関する学びの模索が始まっています。個人と地域のウェルビーイングを支えるライフスキルとその学びについて、コンパッションとケアリングという文脈から考えていきたいです。
[*1]ケララモデル
診断名・年齢・社会階層に関わらず、不治の病、寝たきり、死にゆく患者の問題に、地域コミュニティが参画する医療サービス提供により対応する緩和ケアの仕組み
[*2]Institute of Palliative Medicine(IPM)
インドのコジコード(英名:カリカット)にある地域密着型緩和ケアの実践・研修・研究を行う機関。
発行日 2025年9月1日
発 行 NTT株式会社
編集長 渡邊淳司(NTT 上席特別研究員)
編 集 矢野裕彦(TEXTEDIT)
デザイン 楯まさみ(Side)