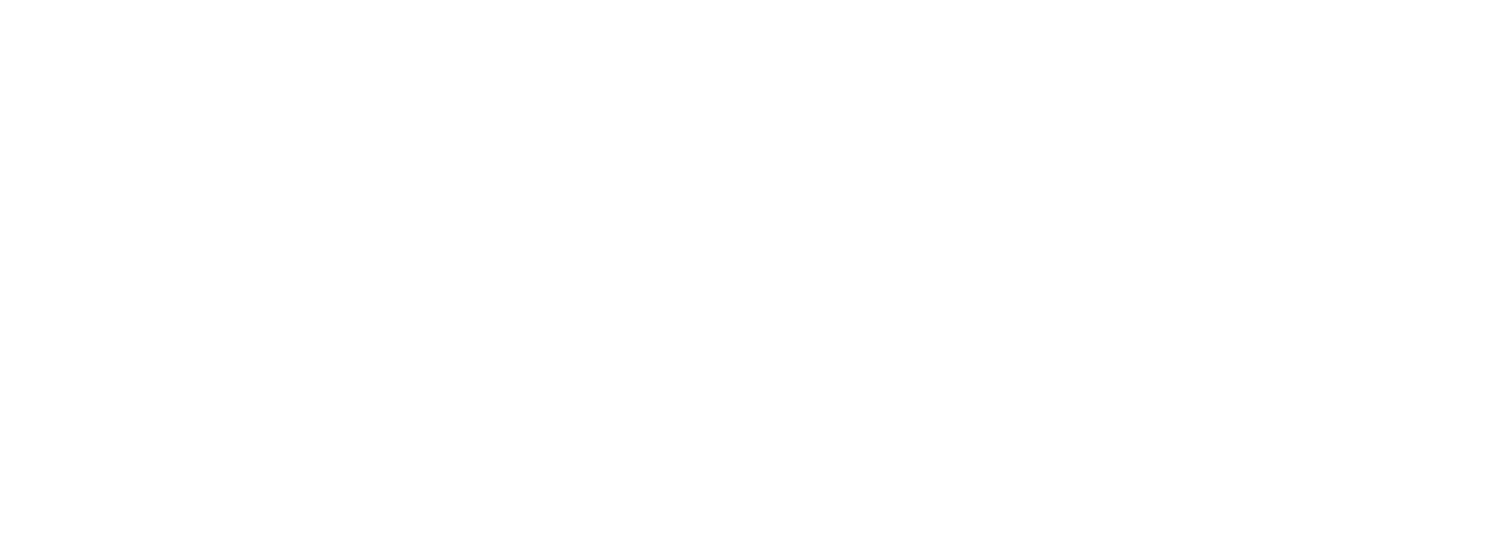


理化学研究所 チームリーダー、株式会社ハコスコ代表取締役、VRコンソーシアム代表理事
1965年広島生まれ、東北大学医学部卒。東北大学病院眼科、マサチューセッツ工科大学での勤務を経て、2004年より理化学研究所所属。ハコスコでのVR事業経営と並行し、VR領域における啓蒙活動を行う。
人間の社会性を研究するために
先生の研究についてお聞かせください。
藤井: 僕はもともと猿の社会性を研究していました。どんな動物にしろ、社会性を持っている動物は、一人でいる時と相手といる時で振る舞いが変わります。ただそこにいるだけの他人という存在が、自分の行動を変えてしまう。その仕組みを理解したいと思って始めたのが社会性の研究でした。初めに、脳の研究ができて分かりやすい社会性を持つ動物として、猿を選んだんです。猿のあとに、同じことを人でもやろうと考えました。ただ、そこでは、まったく同じ社会的な刺激を被験者に与えなければならないという課題がありました。例えば毎朝、僕が誰かに「おはよう」と言います。でも相手にとっての僕は毎回違うはずなんですね。「現実」は一度しかなくて、繰り返しできないから、社会性の実験を人でやろうとしたら、「現実を繰り返さないとできない」という結論に達して、無理かなって思ったんです。
最初はCGのアバターと会話するみたいなことをやったんですけど、CGが相手だと何の関係性も生まれないんです。どうしようかなと思ってる時に出てきたのがSR(Substitutional Reality:代替現実)でした。ヘッドマウントディスプレイを付けて、現在と過去の映像を気づかないうちに何度も切り替えることで、体験者は、目の前に見えていても、その人が本当にいるのか、いないのか、区別がつかない状態を作ることが可能になったんです。これで実験ができるようになったんですけど、一方でSRでいろいろやってたら面白かったんで、実験よりも興味がそっちのほうに(笑)。
SRを使った3つのパフォーマンス作品
SRを使ってどのような作品を作られたのでしょうか?
藤井: SRを使って、最初「MIRAGE」*1というパフォーマンス作品を作りました。ただし、MIRAGEをやるためには、常にパフォーマーが二人いる必要があり、それがコスト的にも、パフォーマンス的にも大変で、2年くらいずっと悩みました。次に、パフォーマンスはなくして、体験者そのものをスクリーンに映して見せてあげて、その人の時間軸を操作すると、何か変なことが起きるんじゃないかなと思って作ったのが「The Mirror」*2です。展示としては、コストもかからず、最初に説明をするだけでいいのですが、逆に人の存在感が少なくなり、SRの面白さが減っちゃったんです。
1.「MIRAGE 」(GRINDER-MAN、2012)
SRシステムを応用し、藤井氏のサイエンスディレクションに基づき、パフォーマンスグループGRINDER-MANが製作した没入体験型パフォーマンス作品。体験者はヘッドマウントディスプレイとヘッドホンが組み込まれたデバイスを装着し、2名のダンサーとリアルタイムにインタラクションする。過去に記録されたダンサーのパフォーマンスと目の前で行われているパフォーマンスが、気づかないうちに何度も切り替わり、体験者は現在と過去を行き来する。

2.「The Mirror」(Naotaka Fujii + GRINDER-MAN + evala、2015)
SRシステムを応用し、藤井氏が製作・監修、タグチヒトシ氏(GRINDER-MAN)が構成・演出・映像、伊豆牧子氏(GRINDER-MAN)が振付・出演、evala 氏が音楽・サウンドデザインを行った没入体験型作品。体験者はヘッドマウントディスプレイとヘッドホンが組み込まれたデバイスを装着し、正面のスクリーンの中にある「今」「近い過去」「過去」、環境にある「今」と「過去」という合計5種類の時間を行き来する中で、「今、ここ」の感覚を揺るがされる作品。
【Photo by Masaki Miyai / Photographs courtesy of Contemporary Art Museum, Kumamoto】
そこで、生身の人と人との関係自体に影響を与えたいと思い、体験者と体験者のインタラクション、さらにダンサーとのインタラクションを加えたらどうなるかと考えました。それで生まれたのが「Neighbor」*3という作品です。お互いを知らない男女の体験者に、手を握り合ったり、インタラクションしてもらい、そこにパフォーマーが映像上で入れ替わったり、踊ったり、いろいろと介入してくるという内容です。

3.「Neighbor」(Naotaka Fujii + GRINDER-MAN + evala、2016)
「The Mirror」と同様、藤井氏が製作・監修、タグチヒトシ氏(GRINDER-MAN)が構成・演出・映像、伊豆牧子氏(GRINDER-MAN)が振付、evala氏が音楽・サウンドデザインを担当。体験者2名と現地ダンサー2名とがインタラクションする没入体験型パフォーマンス作品。
【Photo:from http://grinder-man.com/2016/neighbor】
体験者はどのような反応をしたのでしょうか?
藤井: 体験した二人には、作品を一緒に共有したという一種の吊り橋効果のような影響があって、終わった後に妙に仲良くなるという現象がありました。実際、終わった後に初めて会った人同士が仲良くなったり、例えばカップルで来場した二人のうちボーイフレンドのほうだけが参加して、相手は別の女性だった場合、体験が終わって二人が仲良くなっちゃうと、外で見てるガールフレンドが怒っちゃうんです。特に怒るようなことは何もしてないんだけど、何かそういう影響を与えているのは面白いですね。加えて、作品の中では、この瞬間から手をつながなきゃいけないというプレッシャーやインストラクションは特に強く与えてないんですけど、うまく手をつなげただけで、体験者は不思議な達成感を感じたりします。外から見ていても、うまく手を繋げた人を見ると「やった!やった!」ってなるんです。