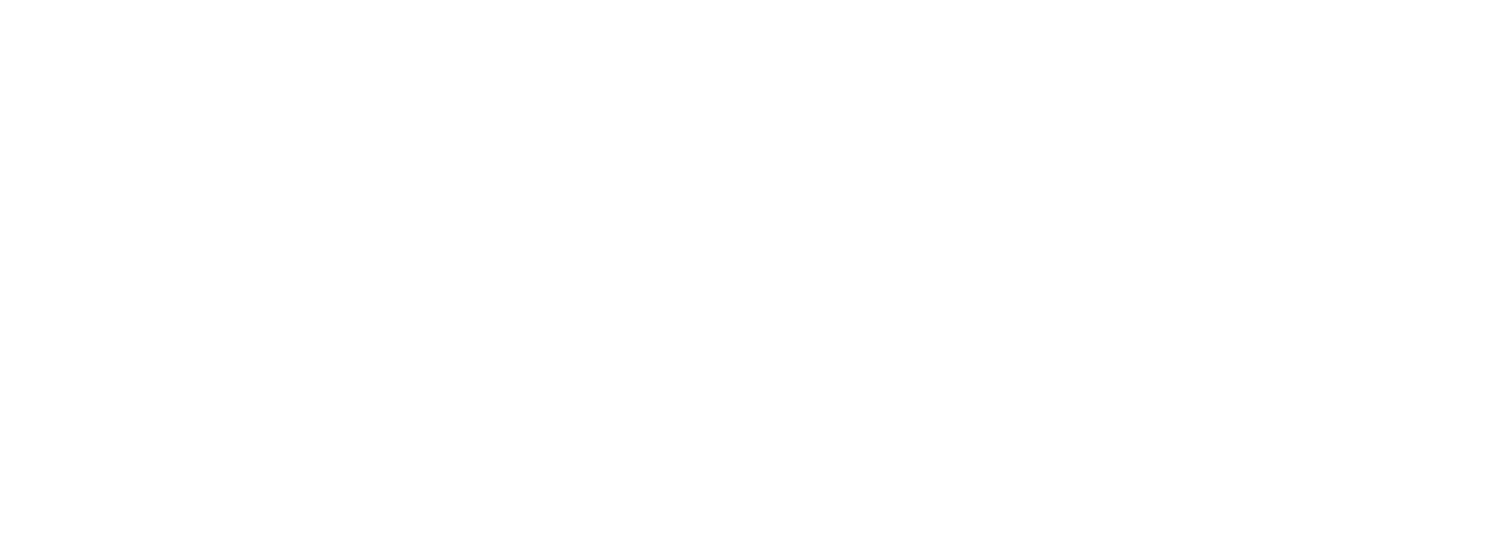
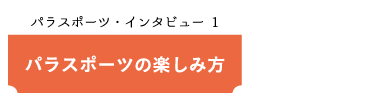
「する」「見る」「支える」
パラスポーツから生まれる
共感と違いの認識
東京オリンピック・パラリンピックを控え、注目が集まりつつあるパラスポーツ。これまでパラスポーツに接したことがない人にとっては未知の世界です。正直なところ、どんな態度で観戦したらいいのか、その心構えすらわかりません。そこで、NPO法人STAND代表の伊藤数子氏にパラスポーツの捉え方について話を伺いました。

誰もが明るく豊かに暮らす社会の実現を目指し、2005年にNPO法人を設立。障がい者スポーツ事業を開始する。NPO法人STAND代表理事/東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会顧問。
「さらし者」という言葉をきっかけに動き出したNPO活動
—パラスポーツ体験会やボランティア・アカデミーの開催など、現在の活動を始めるきっかけを聞かせてください。
伊藤:パラスポーツを通して共生社会を目指そうと、2005年にNPOを立ち上げました。2003年に電動車椅子サッカーを観に行ったのですが、そのチームが遠征することになり、遠くまで観に行けない人たちのために、試合をインターネットで中継することにしました。ところが、会場で「障がい者をさらし者にするなんて、どういうつもりだ!」と怒鳴られたんです。一瞬「たいへんなことをしてしまった」と思いましたが、その言葉には大きな違和感が残りました。「さらし者」とは、「人前で恥をかかされた人」という意味です。では障がいがあるスポーツ選手は、プレーを中継されることで、人前で恥をかかされているのでしょうか? そんなはずはありません。パラスポーツを知る人がもっと増えれば、社会が少し変わるのではないかと考え、パラスポーツをもっと中継しようと思うようになりました。
—2020年のパラリンピックは、パラスポーツを知ってもらういい機会となりますね。
伊藤:確かにそうです。私たちの活動は、スポーツの支援やPRではなく、スポーツをする姿を「さらし者」と言わない社会をつくりたいという目的から始まっています。近年は体験会を中心に展開しているのですが、そんな中で東京でのパラリンピック開催が決まったんですね。実際、パラスポーツを知る人が増え、「すごい」とか「迫力がある」と言う言葉も耳にするようになりました。オリパラのコンセプトにも「共生社会を目指す」という言葉が出てくるなど、そういう風潮になってきたことを感じます。ただ一方で、「パラスポーツを広めること=共生社会になる」といった単純なモデルが広まりつつあるのではないかという危惧もあります。
「“ 障がいがあるのに” すごい」から種目のひとつとして捉える目線に
—パラスポーツを観て「すごい」と思ったとしても、その感覚に危うさもあると?
伊藤:もしかしたら、その「すごい」には、前提があって、「“ 障がいがあるのに” すごい」と思ってる人が多いのではないでしょうか。少しきつい言い方になりますが、障がいがある人に対して「自分より能力が低い、だけどすごい」という考え。そこで立ち止まってしまったら、共生社会にはつながりません。
—そのことを踏まえた上で、パラスポーツ観戦の理想とはどのような状態だとお考えですか?
伊藤:先に結論を言うと「普通に観る」ということなんです。パラスポーツって面白そうだと思った人が行く。映画を観に行くように、野球を観に行くように、今日はブラインドサッカーの観戦に行こうというふうに、アクティビティの選択肢として並列に並んでいるのが理想ですよね。
—一般のスポーツとして、その選択肢のひとつになるのが理想ということですね。
伊藤:そうですね。車椅子バスケの場合、実は国内の大会では障がいがない人でも出場できます。例えば、スキーは道具としてスキー板やストックを使いますよね。それと同じで、車椅子バスケという競技には道具として車椅子が必要という考えです。
—種目として捉えるとわかりやすいですね。
伊藤::「障がい者スポーツ」とか「パラスポーツ」という言葉そのものが不要になる時代が、いつか来てほしいという気持ちはあります。ただ、大会を運営するときに、それがいいかどうかは別の話です。組織体系化する場合には、やはりカテゴライズが必要だと思いますが、私たちの頭の中では「男子100、女子100、男子車椅子100」といった具合に、並べて考えられるようになったらいいなと思いますね。

NPO法人STAND では、パラスポーツの体験会などを積極的に行っている。パラスポーツを共生社会のためのソリューションとして捉え、スポーツを通して共感し、障がい者とふれ合うことで理解を深めることをひとつの目的としている。
共生社会の入り口としてパラスポーツを選ぶ理由
—パラスポーツを通して共生社会を目指すメリットは何でしょうか?
伊藤:スポーツには、「する」「見る」「支える」という観点がありますが、どの点から見ても共通するのが、“ 共感” だと思います。スポーツの場合、お目当ての選手やひいきのチームの応援のために会場に来る人がいる一方で、特に好きな選手もチームもないけれど、友だちに付いて来たという方もいますよね。そういう人でも、試合を見ているうちにどちらかのチームや選手を応援していませんか?これがスポーツの面白いところで、必ずどちらかを応援しているんです。そして、応援している人同士というのは共感するんですね。点が入れば周囲にいる見ず知らずの人とハイタッチしたりして、みんなで大喜びする。スポーツは、そんな現象が起きる場所なんです。また別の観点では、「肉体の違い」を目の当たりにするということもあります。スポーツの場合、体の形状の違いがはっきりと見えますし、体の可動範囲もわかります。見ている人に「あ、ここが違うんだ」ということがダイレクトに伝わるわけです。見慣れていくことで、違いを受け入れ、見ている側のバリアをなくしていくことにつながります。
—それは、違いをきちんと理解するきっかけになるということでしょうか?
伊藤:そうですね。初めて自分と違う身体の人を見たらショックを受けるものです。だからこそ、見慣れていくことは大事なことではないでしょうか。「ああこんなふうに動く、または動かないんだ」「こんな形なんだ」と知ること。スポーツは体や身体能力の違いを理解する上では、近道のひとつなのではないかと思います。
2020年のパラリンピックを一瞬の祭りで終わらせない
—パラリンピックに関わる組織は多数ありますが、終了後に解散したり、縮小したりすることになりますよね。
伊藤:そのとおりです。国や自治体、企業もそうですが、関連セクションがなくなります。ミッションがなくなり、予算がなくなり、人がいなくなる── これは、仕方がないことです。ただ、そこで培ったDNAを残してほしいんです。例えば、企業内に設置した“2020推進部” はなくなっても、そこで育んだ考え方を何らかの形で、会社の中のどこかに残し、共生社会への取り組みを続けることはできないだろうかと思いますね。
—オリンピック・パラリンピックの開催によって生まれたものを、どんな形で残していけるでしょうか?
伊藤:私が関わっているある自治体には「2020年オリンピック・パラリンピック課」があります。その課もやはり時限式です。2020年のオリパラを機にボランティアとして集まった人たちを束ねる運営事務局がなくなるわけですが、そのDNAをどこかに残しておけないかという思いで任意団体を作り、ボランティアをやっています。これは、公的組織ではない人の集まりなので、やめない限り続きます。最近、その中に「女子会」を作りました(笑)。あまり組織立てたりはしていません。こういうゆるいつながりの中で考えをやり取りし、パラリンピックのあとにもそのDNAを残せる場所になってほしいと思っています。

パラリンピックの開催は多くの人がパラスポーツに触れる機会となるが、そこで生まれた共生社会のDNAをどうやって未来につないでいくかということを意識してほしいと、伊藤氏は言う。